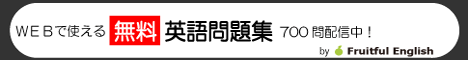- ホーム
- 活動履歴
- ハリネズミについて
- ハリネズミ健康手帳
- ハリネズミ情報登録
- フード・おやつ
- ♥フードサービス注文♥
- 【特集】成分・材料について
- フード各種 >
- ハリセレブごはん/ハリネズミの隠れ家
- 恵ハリネズミ/ハイペット(株)
- ハリネズミフード/(株)三晃商会
- ハリネズミセレクション/イースター(株)
- ハリネズミセレクションプロ/イースター(株)
- 動物村ハリネズミフード/イースター(株)
- THE・PERFECT ONE ハリネズミ専用フード/マルカン
- casa ハリネズミレシピ/マルカン
- トリプルバランス/マルカン
- Animal Premium Pack ハリネズミ
- ハリネズミ専用フード Fay/Tiny Tot Tail
- メディ ハリネズミ/ニチドウ
- 8 in 1 ウルトラブレンド・セレクト ハリネズミフード/スペクトラムブランズジャパン(株)
- ハーリーの主食/R.D.B
- ハーリーの主食グロース/R.D.B
- ひかりハリネズ/(株)キョーリン
- 大地の恵み ハリネズミフード/(株)コジマ
- メディマル ハリネズミフード/有限会社メディマル
- ジクラ アギト ハリネズミ専用フード /有限会社ジクラ
- Fラボ/日本ペットフード株式会社
- インセクティボアフード/Mazuri
- カントリーミックスExハリネズミフード
- おやつ各種
- 栄養補助食品各種 >
- 強制給餌について
- 飼育環境
- 病気・健康チェック
- 強制給餌
- 防災・引越し
- 出産・赤ちゃん
- 各MAPまとめ
- オリジナルグッズ
- ブログ
- 当協会について
- 問い合わせ・SNS
- リンク
- 支援金
ヨツユビハリネズミについて

日本で飼育することができるハリネズミは、「ヨツユビハリネズミ」と呼ばれ、哺乳類の中の ハリネズミ目➤ハリネズミ科➤ハリネズミ亜科➤アフリカハリネズミ属に分類されます。俗称としてピグミーヘッジホッグとも呼ばれます。ペットとしてはおなじみになりましたが、野生での暮らしについてはまだ明らかになっていません。
基本的には、ハリネズミは単独生活を好みます。他のハリネズミと一緒になるのは、繁殖時と子育てをするときだけです。夜行性で、夕方や夜明け前にも活動しますが、最も活発なのは、午後9時~0時、次いで午前3時とされます。活動中はほとんどが食べ物探しに費やされ、一晩のうちに3~5kmも歩き回ると言われています。なわばりをもつかどうかは不明です。生活空間は、地面の上で、木に登ることはないようです。乾燥した場所の、岩の下、低木の茂み、木の根の間、朽ちた丸太の下などを巣にしています。
※ペットとしての飼育下でも、野生時の生活環境を加味して考えることが大切だと思います。
おもに昆虫、ミミズ、カタツムリやナメクジなどの無脊椎動物を食べます。他、カエル、トカゲ、ヘビ、小型哺乳類、死肉のほか、果実、種子、キノコなど動物質に限らずたべます。一晩で体重の30%にあたる量を食べるようです。
※飼育環境下のハリネズミは、野生とは運動量が異なります。体重の5~10%を目安にごはんをあげ始めてみてください。食べきれる量と食べきれない量、ごはんの種類など、適した量と種類を探ってみましょう。月1回以上体重を測り、成長期を除き、増え続けていないか、逆に減少し続けていないか様子をみてごはん量の調整もしましょう。
ヨツユビハリネズミは冬眠はしませんが、お腹や身体が冷えてくると、動きが著しく弱くなり、時折痙攣のような様子を見せることがあります。これは低体温症です。また、熱い季節(約30℃以上)になると、夏眠したり、熱中症になることも。夏眠は、食べ物が足りなくなる乾季を乗り切るしくみです。
※飼育下のハリネズミは低体温症・夏眠とならないよう、温度湿度調整に気を配りましょう。
ハリネズミのしぐさついて

未知の物体と出会うと、それを舐めて口の中で泡状のだ液と混ぜて、長い舌で背中やわき腹の針に塗り付けます。理由ははっきりわかっていませんが、説として「自分のにおいを隠して周辺と同じにするため」「繁殖相手を引き寄せるため」「毒性の物質と混ぜて塗ることで天敵から身を守る」など考えられます。

ハリネズミのあかちゃんですが、アンティングの様子を提供いただけましたので、よかったらご覧ください★
驚いた時、不快な時、不安な時などに、警戒すると針を立てます。
①針が寝ている(通常)
②おでこの針だけ立てる(少し警戒)
③全身の針を立てる(警戒高)
④完全に丸まる(警戒MAX!)

意外といろいろな声を発するハリネズミ!知っておくとコミュニケーションに役立つでしょう。特に異常を訴える場合もありますので、鳴き声には特に注意を払いましょう。
【警戒している】
「フッフッ…」と短いピッチで立て続けに鳴く。丸まりながら「フシューフシュー」いうことも。
【探検中】
探検したり、食べ物を探しているとき「フンフン」と鼻を鳴らします。
【リラックス・ご機嫌】
「クックッ♪」「ゴロゴロ♪」と喉を鳴らします。
【求愛】
オスはメスの回りをまわりながら気を惹こうとして「ピーピー」と優しい声で鳴きます。
【悲鳴】
恐ろしいことや苦痛と遭遇すると「キュッ!」「キューキュー」「キーキー!」と鳴きます。
特に苦痛の場合は、繰り返し鳴くこともあるので、早急に病院で診てもらいましょう。
※ハリネズミも夢を見るようで、寝てる間にも声を発することが少なくないようです。
「フニャフニャ」や悪夢?でうなされたのか、「フギャッ!」と声をあげることもあります。
【赤ちゃんハリネズミ】
さえずるような、ピッチの早い鳴き声で鳴きます。


ハリネズミには個体差で大小あるものの、巷?ではあごの下に「ハリぽっち」と呼ばれる突起があります。役割や詳細は不明です。⚠️徐々に大きくなったり、赤く腫れた様子だったり、変化があるようですと、ハリぽっちではない可能性がありますので、その場合は病院で診てもらいましょう!
【誕生】
1回の出産で、平均3~4匹の赤ちゃんが産まれます。赤ちゃんの体長2.5cm、体重10~18gです。
【生後2日目:針の成長】
産まれるとすぐ、皮膚の下に隠れていた針が出現!丸一日で生えそろいます。針5mm前後に。
【生後8~13日目:防御の行動】
まだ目を開いていませんが、体を丸めたり、シューシュー威嚇する、だ液塗りしたりできるように。
【生後14日:目が開く】
目が開き、ふさがっていた耳の穴も開きます。もう少しすると体毛も生えてきます。
【生後18日:歯が生える】
乳歯が生えてきます。9週目までには生えそろい、永久歯は7週くらいから生え始め、置き換わります。
【生後6週目まで:大人の針になる】
針には、生まれたときの針、2~3週目の針、大人の針と3種類あります。
【生後6~8週目…離乳】
母乳から徐々に固形のフードを食べるようになり、しっかり固形の食事が食べられるになれば離乳です。母親から自立できます。
【生後2か月以降:性成熟】
およそ生後2~6か月で性成熟し、オスもメスも子どもが作れるようになります。離乳した後、赤ちゃん同士、もしくは母親ハリネズミと一緒にいると、繁殖してしまうことがあります。
子どもたち同士、親子同士での交尾を避けるため、1か月を目途に様子を見てケージを分けましょう。例えば、オスがピーピーと小鳥のように鳴くのは求愛行動です。気を配りましょう。


生後6週間(1~2か月間)までの間に、針が生まれ変わります。ご紹介している針の写真では、約1.0cm➡1.2cmに成長したことがわかります。また、その際に、たくさんの針が抜ける現象が起こります(クイリングと呼ばれる生理現象)。数回繰り返し起こる場合もあります。ダニやカビと違い、フケは出ず毛根もきれいなのが特徴です。病気ではないので、成長の一環として見守りましょう。
●体重…300~600g
●寿命…2~4年
●体温…35~37℃
●心拍数…180~280回/1分
●呼吸数…25~50回/分
※個体差があります。
補足資料

外来生物法について
【外来生物法とは?】
特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資するための法律として、2005年に制定されました。
【特定外来生物法とは?】
外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。
実態がよく分かっていない海外起源の外来生物は「未判定外来生物」に指定され、輸入する場合は事前に主務大臣に対して届け出る必要があります。外国から生物を輸入する場合、税関でその生物が特定外来生物又は未判定外来生物かどうかをチェックすることになります。
特定外来生物による被害がすでに生じている場合又は生じるおそれがあり、必要であると判断された場合は、国または地方自治体が、主務大臣の確認を受けて、特定外来生物の防除を行います。国が防除を行う際に、その原因となった行為(逃がしてしまったなど)をした者に対しては、防除に必要な費用の一部又は全部を負担していただく場合があります。
【ハリネズミへの特定外来法適用】
以前は、マンシュウハリネズミなど、数種のハリネズミがペットとして飼育されていたそうですが、飼えなくなったハリネズミを野外に放したり、脱走してしまったりすることで、国内の一部に野生化し、住み着いたと考えられています。その結果、生態系や農作物への影響を懸念し、このように外来生物法で規制されることになってしまいました。ヨツユビハリネズミも、同様の道を辿らないとも言いきれません。飼育に規制はなくても、もともとヨツユビハリネズミも、日本にはいない外来生物であることを認識していただき、責任をもって最後まで飼育してください。
参考:環境省>自然環境局 外来生物法とは? https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/index.html
【参考文献】
大野瑞絵著・三輪強恭嗣監修「ハリネズミ 完全飼育」誠文堂新光社(2016)
大野瑞絵著・三輪強恭嗣監修「ザ・ハリネズミ」誠文堂新光社(2009)
大島圭子編集「ハリネズミ飼いになる」誠文堂新光社(2014)
高橋剛広・田向健一監修「かわいいハリネズミと暮らす本」エムピージェー(2017)